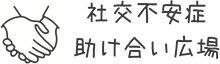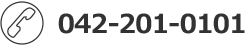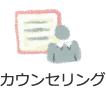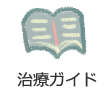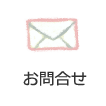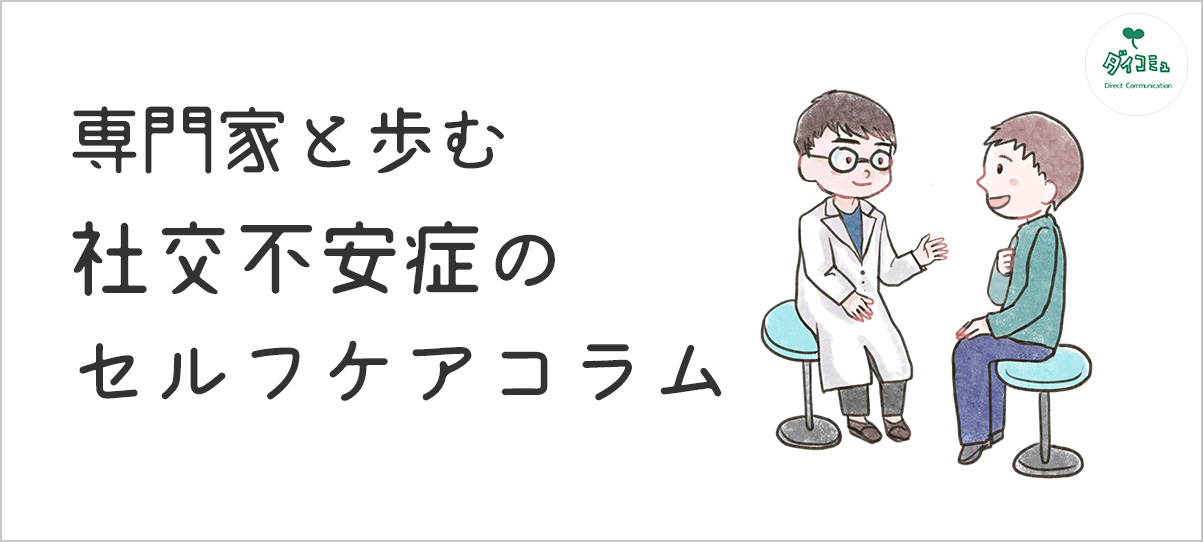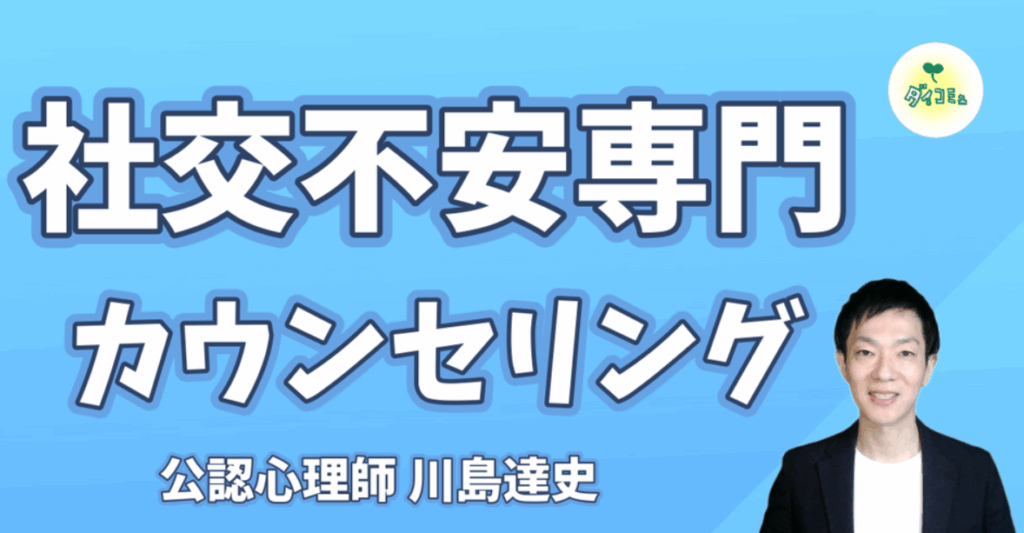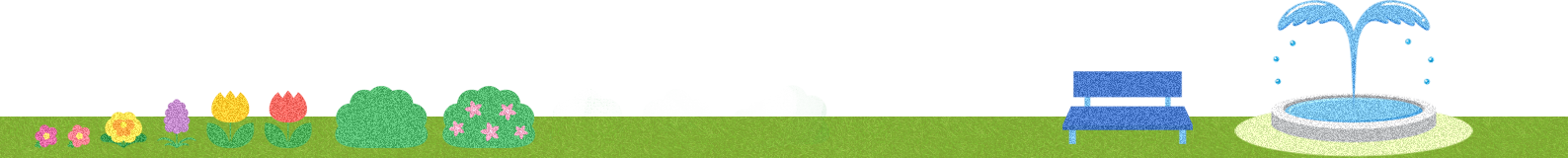こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。この記事では、社交不安症について基礎から解説します。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。
今回のテーマは①基礎編の「白黒思考,ゼロ百思考をやめたい方へ」です。 社交不安症には様々な症状が出たり、関連する精神感があります。今回は全体として理解していく回となります。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。
白黒思考の特徴・具体例
白黒思考とは、物事を「白か黒か」の二極で極端に捉えてしまう思考のクセです。どちらともいえない「あいまいな状態」に対して強い不安を感じやすくなってしまいます。
白黒思考が強い方は、ちょっとした出来事でも極端に判断してしまうので「少し失敗した=すべてがダメ」と考えてしまいがちです。中間的な捉え方ができなくなってしまうので、不安や恐怖心が強くなってしまいます。
白黒思考によって不安が膨れ上がり、人間関係をリセットしてしまうほど心が追いつめられてしまうこともあります。
白黒思考の具体例
白黒思考が強い人は、どのような場面で戸惑うのでしょうか。いくつか事例を紹介します。
具体例①SNSでの既読無視に敏感

相手からメールの返信がない、LINEで既読が付いたにもかかわらず返信がしばらくないといった状況を、「嫌われた」「もうだめだ」と即座に判断してしまい、不安が膨らんだ結果、SNSを断捨離してしまう。
具体例②飲み会で孤立

飲み会で孤立をすると、「暗いやつだと思われた」「いいことが何もない」など極端に考えてしまい、その後の飲み会や食事会を徹底的に避けるようになる。
具体例③恋愛での価値観のズレ

食事の好みが全く違うカップルがいたとします。白黒思考が強い方は、食事の好みが合わないから一緒にはやっていけないと考え恋愛関係を早々に終わらせてしまう。
このように、白黒思考がある方は、0か100かで物事を判断しやすいため、不安や恐怖が強まりやすく、不安がピークに達すると人間関係を手放してしまうことがあります。
白黒思考を緩める方法
白黒思考を緩めるには、曖昧さ耐性を付けることが大切です。曖昧さ耐性とは、曖昧な状況に耐えられる心理のことで、あいまいな状況を面白がったり、楽しんだりできる状態を指します。
0か100かで考えられない中途半端でボヤッとした状況でもその状況をそのまま楽しんだり、そのままにしておける心理です。曖昧さ耐性をつける具体的な方法はこちらです。
①人間関係はグレーが基本
②リセットせず粘る
③楽しむ勇気を持つ
詳しく見ていきましょう。
①人間関係はグレーが基本
「人間関係はグレーが基本」という視点をもつようにしましょう。人の心は単純に「白か黒か」で分けられるものではなく、「好きでもあり嫌いでもある」といったように、複雑な感情が混ざり合っているのが自然な状態です。そのため、「0か100か」で人間関係を割り切ることは、現実的ではないと考えることが重要です。
たとえば、先ほどの例で白黒思考が強い方は、「返信がない=嫌われた」と結論づけてしまいがちです。しかし、曖昧さ耐性を持って考えると、「体調が悪いのかもしれない」「気分が落ち込んでいて返信する元気がないのかも」など、さまざまな可能性があると捉えることができます。
確かに、自分に対する好意が薄れた可能性もゼロではありません。しかし返信がないだけで「軽視された」「興味がない」といった結論を出すことは難しく、根拠にも乏しいのです。
ここで重要なのは、いくら考えても明確な結論は出せないということです。限られた時間のなかで、毎回明確な答えを求め続けるのは非効率ですから、「いくら考えても結論は出せない」「相手の気持ちはよくわからないままにしておく」という感覚を持つことが大切です。
SNSを断捨離する必要はありません。返信がないという「曖昧な状態」を、そのまま受け入れる余裕を持てると、心が少しラクになります。
②リセットせず粘る
すぐに人間関係をリセットせず、ある程度粘り強く関わり続ける姿勢を持つことです。白黒思考が強い方は、不安や恐怖に耐えることができず、コミュニティをリセットしたり人間関係を断捨離してしまう傾向があります。
たとえば、先ほどの飲み会の例では、白黒思考の方は、孤立したことで「もう参加しても意味がない」「自分は必要とされていない」と極端に考え、その後の参加を避けてしまいました。
しかし実際には、参加するだけで周囲に安心感を与えたり、空気を和らげたりと、見えない形で貢献していることもあります。誰かがうなずいてくれるだけでも、話す側は心地よさを感じるものです。
「今回はうまくいかなかったけど、次は少し話せるかもしれない」といった気持ちで、関係を続けてみることが大切です。結論を先延ばしにして、グレーなまま関係を続ける。このようにリセットせず粘る強さが、長期的な人間関係の土台となっていきます。
③楽しむ勇気をもつ
曖昧さ耐性がある人は、不確実で中途半端な状態に対しても、興味や好奇心を持ちやすいという特徴があります。
たとえば、先ほどの食の好みが合わないカップルの場合、白黒思考の方は「食の価値観が合わない=一緒にやっていけない」とすぐに切り捨ててしまいました。一方で曖昧さ耐性を持つ人は、「このギャップが今後どう影響していくのか?」「意外と歩み寄れるかもしれない」といったように、わからなさそのものを楽しもうとします。
白黒思考は、「不安や恐怖から早く解放されたい」という思いの裏返しでもあります。しかし、こうした感情を人生の一部として受け入れ、時に楽しむことができれば、人間関係はずっとラクになります。相手の気持ちが読めない曖昧さをあえて楽しむ勇気をもつことで、曖昧さ耐性が育っていきます。
次回のコラムに進む
今回は社交不安症の基礎編⑧を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。
「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。
カウンセリングのご案内
筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。