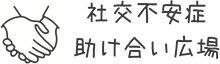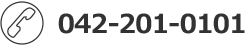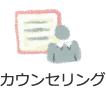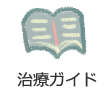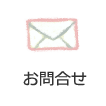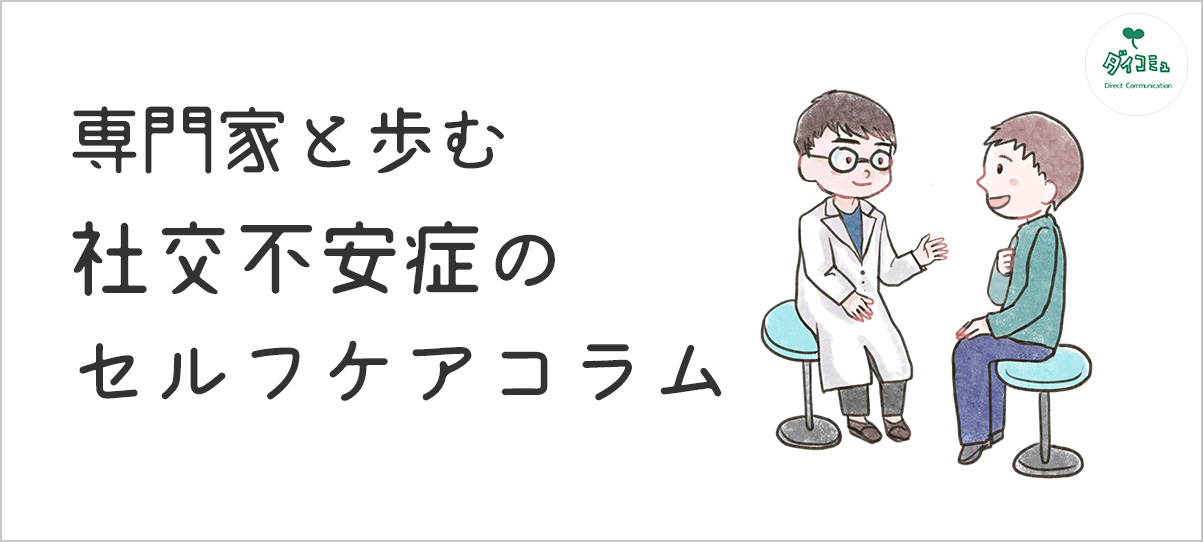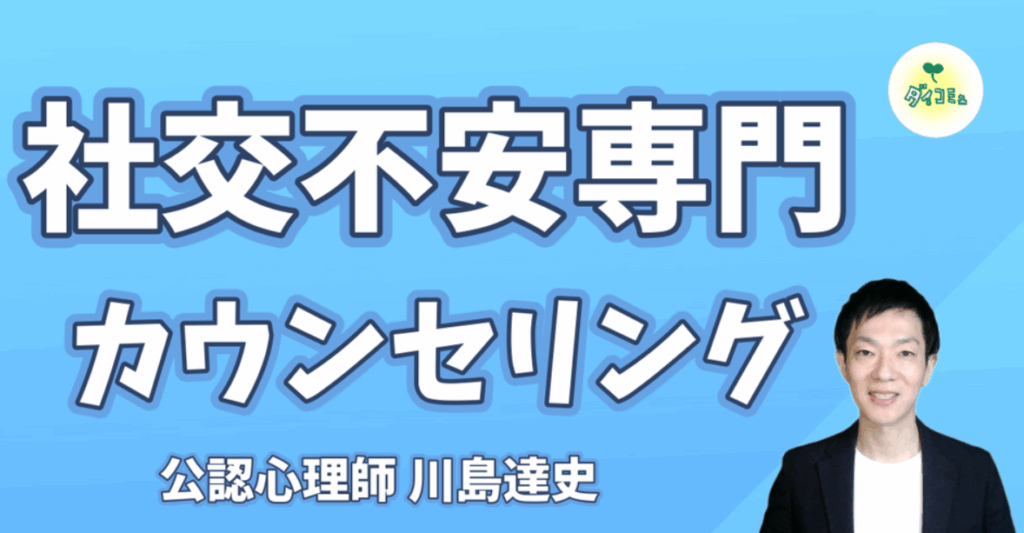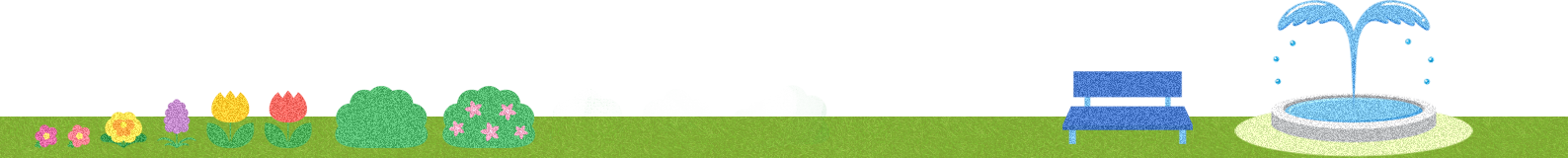こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。この記事では、社交不安症について基礎から解説します。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。
今回のテーマは①基礎編の「自己関連付けの原因や治し方」です。 社交不安症には様々な症状が出たり、関連する精神感があります。今回は全体として理解していく回となります。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。
自己関連付けの特徴と事例
今回は、社交不安を抱える方の思考のクセ「自己関連付け」について解説していきます。
自己関連付けとは
自己関連付けとは、周囲で起こる出来事の原因を、必要以上に「自分のせいだ」と考えてしまう思考のクセです。社交不安のある方は、人間関係で起こるトラブルや失敗を、すぐに「自分の言動が悪かったから」と結びつけてしまう傾向があります。
自己関連付けが強い人は、ちょっとした周囲の動きや言葉を、自分と結びつけてしまいがちです。「何か悪いことをしたのでは?」「嫌われたかもしれない」といった不安や思い込みが膨らみ、人間関係がつらくなっていきます。ここでは、事故関連付けが強い場面の事例を見ていきましょう。
具体例①上司と同僚のひそひそ話が気になる

たとえば、職場で上司と同僚がひそひそ話をしている場面を見たとします。自己関連付けが強い方は、このひそひそ話は「きっと自分の評価を下げているにちがいない」「あのときの失敗の話をしている」「プロジェクトから外されるかも」と考えがちです。
実際には、全く自分とは関係ない話をしている可能性もありますが、「自分のことを言っているに違いない」と思い込んでしまいます。
具体例②LINEの返事が遅いだけで不安になる

自分が送ったLINEやメールに既読がついたのに、しばらく返信がこないときも、自己関連付けが強い人は「私が何か怒らせたかも」「私のせいで返事がない」と考えます。さらに、「きっとあの言葉がまずかったんだ」「もう関わりたくないと思っているのかも」と不安がどんどん膨らみ、気持ちが追い詰められていきます。
具体例③友人の何気ない発言に傷ついてしまう
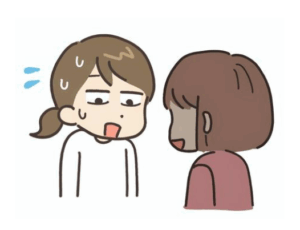
たとえば、友人が「ゆっくり話す人とか、自分から話さない人ってちょっと苦手かも」と言ったとします。自己関連付けが強い方は、「それって私のことだ」「嫌われてるんだ」と思い込み、ひどく落ち込んでしまいます。
このように自己関連付けが強い方は、周囲で何か会話があると「自分のことを言っているに違いない」と感じてしまいがちです。特に悪口を言っている場合には、自分に向けられているものじゃないかと勘違いしてしまいます。人間関係のトラブルをどんどん吸収してしまうため、人と話すのがとても疲れると感じたり、ネガティブなことばかりが起こるように思えて、「もう人と話すのが怖い」と感じることもあります。
自己関連付けを治す3つのポイント
今回は、自己関連づけから抜け出すための3つのポイントを解説します。
①事実と解釈を分ける
まずは、事実と解釈を明確に分けて考えます。先ほどの例で考えると「上司と同僚が話していた」というのは事実ですが、「自分の悪口を言っていたに違いない」は解釈です。現実なのかそれとも自分の中の憶測なのか、しっかりと分けることからスタートさせます。
②他の可能性を考える
次に、「他の話題かもしれない」といった別の可能性にも目を向けてみましょう。自己関連付けをする方は、「○○にちがいない」という感覚が強いです。「ちがいない」というのは考えだけにとらわれず、他の可能性も探ります。他の可能性を考えてみると、自分とは関係ない話や、全く別の出来事について話しているケースの方が多いかもしれません。
③「よくわからない」を受け入れる
例えば、メールが返ってこないのは、自分が原因かもしれませんが、他にもたくさんの可能性がありますから、結論としては「よく分からないから、気長に待とう」と大らかに考えることが大切です。
前回のコラム⑧でもお伝えしたように、人間関係は、白か黒かのように完全に明確にすることは非常に難しく、好きな面もあれば嫌いな面、楽しい面もあれば辛い面もある複雑なものです。
そのため、人間関係はある程度の曖昧さを認めて受け入れることが大切です。最終的には「よく分からない」状態をそのままやり過ごす習慣を持つことが、うまく関係を続けるコツとなります。
事例を見てみよう
3つのポイントを元に、先ほどご紹介した自己関連付けの例を見直してみましょう。
同僚と上司の会話をどう捉えるか

同僚と上司が難しい顔で話しているのを見て、自己関連付けが強い人は「きっと自分の評価を下げているに違いない」と感じたとします。
①事実と解釈を分ける
事実
・上司が難しい顔をしている
・同僚がひそひそ話で報告している
解釈
・きっと自分の悪口を言っているに違いない
事実と推測(解釈)が混ざると、推測が事実のように思えてしまい、不安が大きくなってしまいます。まずはこれらを明確に分けることが大切です。
②他の可能性も考える
推測が不安の原因ならば、「もしかしたら推測が間違っているかもしれない」と考えてみましょう。
例えば、
・仕事とは関係ないトラブルの話をしている
・新年会の予約していた飲み屋が潰れた話かもしれない
・上司と同僚がたまたま野球の巨人ファンで、試合の話をしているだけかもしれない
③「よくわからない」を受け入れる
毎回ネガティブなことを確かめようとしていると、人生がそれだけで終わってしまいます。
例えば、
・上司に「何を話していたの?」と聞く
・同僚を呼び出して「何を話していたの?」と尋ねる
これを繰り返すと、疲れてしまいます。関連しているかもしれないと思ったら可能性を考えても良いですが、最終的には「よくわからないまま」にして、自分のやるべきことを進めていくことが大切です。
返信がないLINEやメールの場合

LINEの既読が付いても返事がない状態を、自己関連付けが強い人は「自分が原因かもしれない」と考えました。
①事実と解釈を分ける
事実
・LINEやメールを送ったが1日返事がない
解釈
・自分が原因で返事が来ないのかもしれない
②他の可能性も考えてみる
・仕事が忙しくて返せない
・メールを見落としている
・体調が悪い
・メンタル的に辛くて返す気分になれない
③「よくわからない」を受け入れる
返事が来ない理由は自分が原因かもしれませんが、他にもたくさん可能性があります。結論としては「よくわからないから気長に待とう」と考えることが重要です。間違っても不安だからといって何度も確かめる習慣はつけないようにしましょう。何度も「なぜメールをくれなかったの?」と相手に確認してしまうと、人間関係がうまくいかなくなることもあります。
返信がないLINEやメールの場合
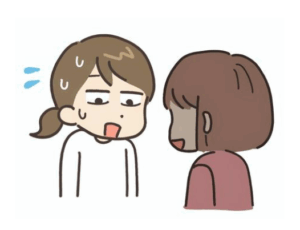
友達が 「ゆっくり話す人って苦手なんだよね。自分から話してくれない人も苦手」といったとしましょう。自己関連付けが強い人は「自分のことを言ってるんだ」「私、何か悪いことしちゃったのかな」と考えてしまいました。
①事実と解釈を分ける
事実
・友人が「ゆっくり話す人が苦手」「自分から話さない人が苦手」と言った
解釈
・それは、自分のことを言っているに違いない
②他の可能性も考える
たとえば「ゆっくり話す人が苦手」だとしても、目の前にいるその人に対して、そんなことを直接言うのはかなり珍しいケースです。しかも、その友人は笑顔で話していたことを考えると、「自分のことを言っている可能性」は、かなり低いのではないかと推測できます。
さらに、その女性の友人にはたくさんの交友関係があり、自分以外の友達のことを言っていたのかもしれませんし、最近会った男性とのエピソードを話していたのかもしれません。
このように考えてみると、「自分のことを言っている可能性」はごくわずかで、他の可能性の方が圧倒的に多いことがわかります。
③「よくわからない」を受け入れる
最後に「本当のところはよくわからない」という結論を受け入れる姿勢も大切です。人の本音や意図は、確かめようとすればするほど曖昧で、毎回確認していたらお互いにとって負担になってしまいます。「まあいいか」と受け流しつつ、普段通りの関係を続けてことがとても大切です。
次回のコラムに進む
今回は社交不安症の基礎編⑨を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。
カウンセリングのご案内
筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。