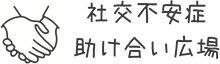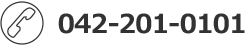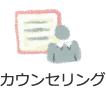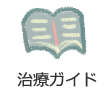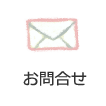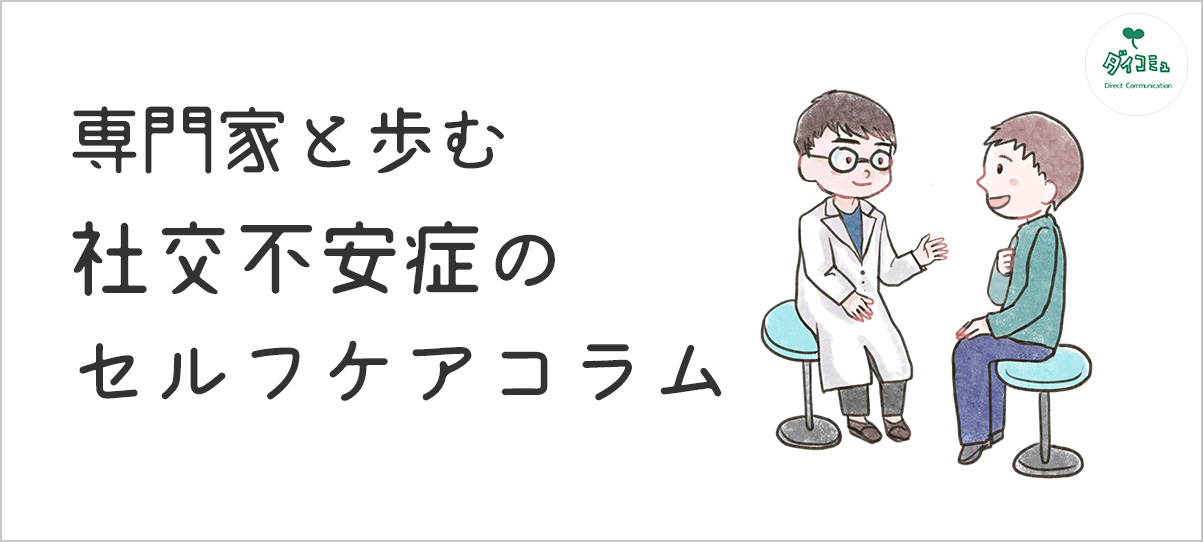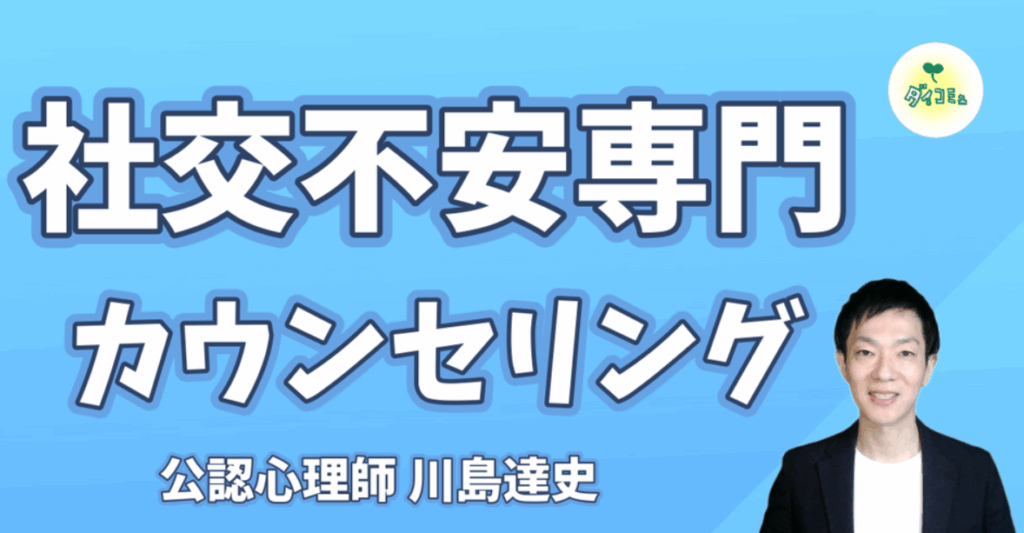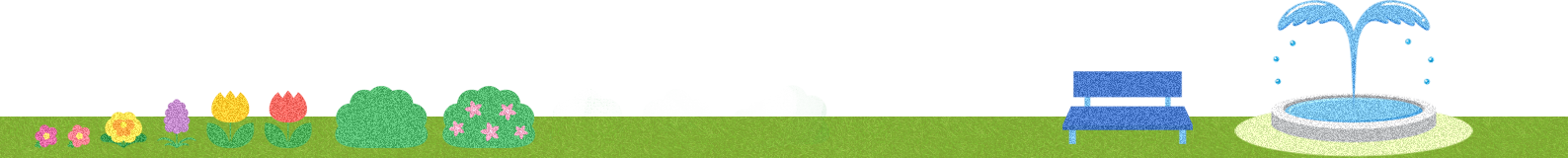こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。この記事では、社交不安症について基礎から解説します。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。
今回のテーマは①基礎編の「拡大解釈・過小評価の治し方」です。 社交不安症には様々な症状が出たり、関連する精神感があります。今回は全体として理解していく回となります。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。
拡大解釈・過小評価の特徴と事例
今回は、社交不安を抱える方の思考のクセ「拡大解釈・過小評価」について解説していきます。
拡大解釈・過小評価とは
拡大解釈・過小評価とは、失敗を必要以上に大きく捉えて、成功を小さくに考えてしまう心のクセです。
何かうまくいかなかった出来事があると、「自分はとんでもない失敗をしてしまった」と極端に悲観的に受け止めてしまいます。一方で、うまくいった経験があったとしても、それをきちんと評価できず、「たまたま運がよかっただけ」「こんなのは大したことではない」と、自分の成果を小さく扱ってしまいます。
他人に対しても影響する考え方のクセ
拡大解釈・過小評価は、自分自身への評価に限らず、他人に対しての見方にも影響を与えます。
自分に対しては、「失敗を大きく・成功を小さく」捉える一方で、他人に対しては「失敗を小さく・成功を大きく」評価しがちです。
その結果、「周りの人はたいした努力をしていないのに、すごい成果を出している」「自分だけがうまくいっていない」といった考えを抱くようになってしまいます。
拡大解釈・過小評価の具体例
拡大解釈・過小評価の具体例を見ていきましょう。
具体例①容姿にコンプレックスを抱える女性
容姿にコンプレックスのある女性のケースです。
女性は、自分の「目が小さい」という特徴を拡大解釈して次のように考えてしまいます。
「自分は目が小さいから、もう絶対にモテることはない」
「目の大きさがすべて。だから私はもうダメなんだ」
このように、自分の一部を必要以上に拡大解釈をし、自分全体の価値のように思い込んでしまうのです。
加えて、成功の過小評価もしてしまいます。彼女は肌がぷるぷるしており、髪が艶やかで綺麗、顔の輪郭が整っていて可愛らしいにもかかわらず、「肌なんて大して影響しない」「髪がきれいでも目が小さかったら意味がない」と、自分の魅力や努力を自ら打ち消してしまいます。
さらに、他人への評価にも拡大解釈・過小評価をしてしまいます。たとえば、「あの人は全然ダイエットもしていないのに、どうしてあんなに綺麗なの?」と感じてしまったり、「みんな目が大きくてコンプレックスもなさそうで、いいなぁ」と羨ましく思ってしまうのです。
具体例②飲み会で孤立してしまった女性
飲み会の場で少し孤立してしまった女性のケースです。
飲み会で「自分だけが話に入れなかった」「全然うまくしゃべれなかった」ことを拡大解釈してしまい次のように考えてしまいます。
「私はなんて社交性のない人間なんだろう」
「こんな恥ずかしい思いをするくらいなら、もう参加しない方がいい」
飲み会で少し会話に入れないことは、誰にでもある自然な出来事ですが、出来事を「大きな失敗」として拡大解釈してしまうのです。
加えて、過小評価もしてしまうため、自分の「できたこと」には目を向けられません。飲み会に参加できたこと、数回話しかけて返答できたこと、自分から話題をふって反応してもらえたことなど、小さな成功や努力があったかもしれません。しかし「孤立していた」「うまくしゃべれなかった」という点にばかり注目し、自分を過小評価してしまうのです。
また周囲に対しては、「みんなは自然に楽しく会話できていて、いいな」「なんであんなにうまく喋れるんだろう」と、彼らの社交性を拡大解釈をしてしまいます。実際には、彼らも緊張を感じていたり、話題を考えるのに努力していたりするのかもしれません。
具体例③成功した昔の友人と自分を比べてしまう男性
昔からの友人と自分を比較して落ち込んでしまった男性のケースです。
子どものころは同じ目線で野原を走り回って遊んでいたような友人が、大人になってから大きな社会的成功を収めたとします。このような場面で拡大解釈・過小評価のクセがあると、次のように考えてしまいます。
「自分はあいつに比べて、全然ダメだ」
「失敗ばかりで、何ひとつうまくいっていない……」
男性は、安定した会社に勤めて堅実に仕事をこなしており、客観的に見れば十分に「うまくいっている」状態であるにもかかわらず、自分の努力や成果を認めることができません。その一方で、相手の成功ばかりに目が向いてしまい、「あの友人に比べたら、自分なんてちっぽけな存在だ」と考えてしまうのです。
このような拡大解釈・過小評価のクセが習慣化すると、自分の失敗だけが大きく見えてしまい、反対に自分の良い部分にはまったく目が向けられなくなります。その結果、自己評価はどんどん下がり、自信がなくなり、対人不安も強まっていくという悪循環に陥ってしまうのです。
拡大解釈・過小評価への対処法
ここでは拡大解釈・過小評価から抜け出すポイントをご紹介します。
①自分に対しての対処法
自分に対しての拡大解釈・過小評価から抜け出すには、「失敗を1回考えたら、成功を2回考える」という習慣を持つことをおすすめします。
たとえば、「自分はなんてダメなんだ」と失敗に目を向けてしまった時には、「いや、ちょっと待てよ。これはもしかすると拡大解釈や過小評価になっていないか?」と冷静に立ち止まり、自分のうまくいった点にも目を向け成功したことを2つ挙げることを習慣化していきましょう。
②他人に対しての対処法
他人の成功を見た時には「あの人は自分にとっての人生の先生だ」と捉える視点を持つことをおすすめします。
筆者が好きな言葉に「麻の中の蓬(よもぎ)」があります。この言葉は、周りの人が前向きでいれば、自分もつられて前向きになれるということわざです。愚痴ばかり言う人に囲まれて過ごすより、努力して成果を出している人たちと関わった方が、自分にも良い影響があるものです。だからこそ、「この人から学ぼう」「お手本にしよう」という意識で、前向きな姿勢を取り入れていくといいでしょう。
また他人への過小評価は「陰で努力していると想像する」ことを心がけてみましょう。「あの人は楽して成功したわけではない。きっと見えないところで努力を積み重ねているのだ」と想像することが、他人への健全な評価につながるでしょう。
事例を見てみよう
ご紹介した対処法を元に、先ほどご紹介した拡大解釈・過小評価の例を見直してみましょう。
容姿にコンプレックスを感じる女性
自分の拡大解釈・過小評価
自分の目が少し小さいという点にだけ意識が向いて、その他の魅力に全く目が向けられないときは、「もしかして、今の自分は拡大解釈や過小評価の思考にハマっているかもしれない」と気づくことが大切です。そのうえで、「とはいえ、自分にも素敵なところはあるはず」と冷静に自分の魅力を探してみましょう。
「お肌がきれい」「髪の毛にツヤがある」「眉が整っていて印象的」など、自分のポジティブな面を少なくとも2つ見つけて、自分で自分を褒めてみます。この意識を少しずつ持つことが、コンプレックスから抜け出す第一歩になります。
他人の拡大解釈・過小評価
他人に対しての拡大解釈・過小評価を和らげるには、相手の成功を先生と捉えて考えてみます。たとえば、以前は周囲のきれいな女性を見て拡大解釈をしたとしても、「この人の服装、私にも参考になるな」「この髪型、真似してみたいかも」といったように、相手をお手本として受け入れる意識を持つことで、前向きな学びに変えることができます。
また、見えない努力を想像することも大切です。その人は、美しさを保つために日々の食事に気をつけたり、運動やヨガを習慣にしていたり、人知れず努力している可能性が高いのです。「楽して手に入れているわけではなく、努力の積み重ねがあるんだ」と、相手の影の努力にも目を向ける姿勢を持つことも大切です。
飲み会での孤立をした女性
自分の拡大解釈・過小評価
飲み会での失敗から「自分はダメな人間だ」「恥ずかしい」とネガティブな感情にとらわれたら、一度立ち止まって「いや、これも拡大解釈かもしれない」とまずは気づくことからスタートします。
次に、飲み会でうまくいったことを考えてみます。たとえば、飲み会に参加できたこと自体が、すでに1つの成果し、「数回は会話できた」「相手が自分の質問に答えてくれた」など、実際にできたこともきっとあるはずです。そうした点に目を向け、「自分なりに頑張れたな」と認識していくことが大切です。
他人の拡大解釈・過小評価
飲み会などで周りの人たちが楽しそうに会話をしているのを見たとき、「この人たちは、どんなふうに会話を展開しているのだろう?」と、自分にとってのお手本として、会話の進め方を観察したり真似してみるといいでしょう。
また、周囲の人たちが自然に楽しく話しているように見えても、実は裏で努力しているのかもしれないと想像してみましょう。「周りの人たちは何も努力せずに自然と楽しくしているんだ」と思い込まずに、「それぞれが気を配りながら、場をよくしようと努力しているんだ」と理解してみることが大切です。
昔の友人が成功していて落ち込んだ時
自分の拡大解釈・過小評価
昔からの友人が大きく成功している姿を見て「自分は失敗ばかりで、何も成し遂げられていない」と感じてしまった時には、「確かにあの人ほどの成功はしていないかもしれないが、自分も地道に勉強し、安定した職に就いて生活しているとまずは認識しましょう。
他人の拡大解釈・過小評価
友人に対しては「どうやってここまで成功したのか学ばせてもらおう」という姿勢を持って接していくことで、自分にとってもプラスになるでしょう。
また、相手の努力もしっかりと認めていく姿勢が大切です。「きっと楽して成功したのではなく、人知れず努力を重ねてきたのだろう」と思えるようになると、相手へのリスペクトと共に、自分自身の心も軽くなっていくはずです。
習慣化で自己肯定感が高まる
対人不安が強い人の多くは、自分に自信が持てず、「拡大解釈・過小評価」の思考パターンにとらわれがちです。失敗にはすぐ気づくのに、うまくいったことや自分の長所にはなかなか気づけない方は少なくありません。
まずはその思考のクセに気づくこと」ができたら、少なくとも2つ、自分がうまくできたこと・努力できたことを挙げる」習慣を持ってみてください。少しずつですが、自己肯定感は確実に高まっていくと思います。
次回のコラムに進む
今回は社交不安症の基礎編⑩を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。
カウンセリングのご案内
筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。