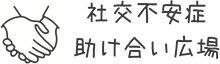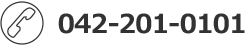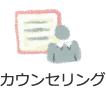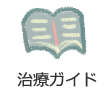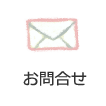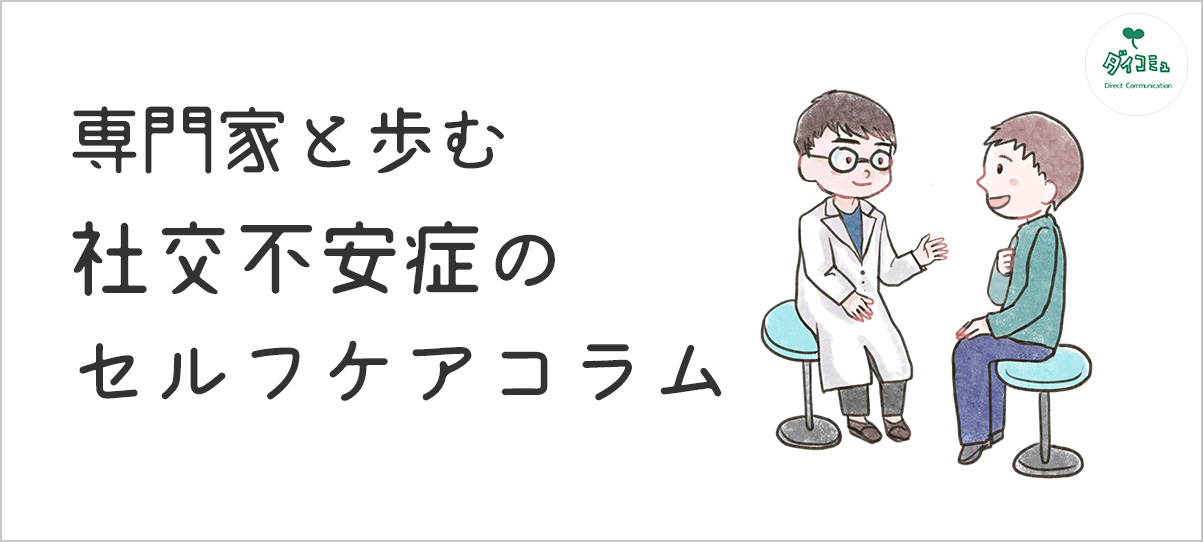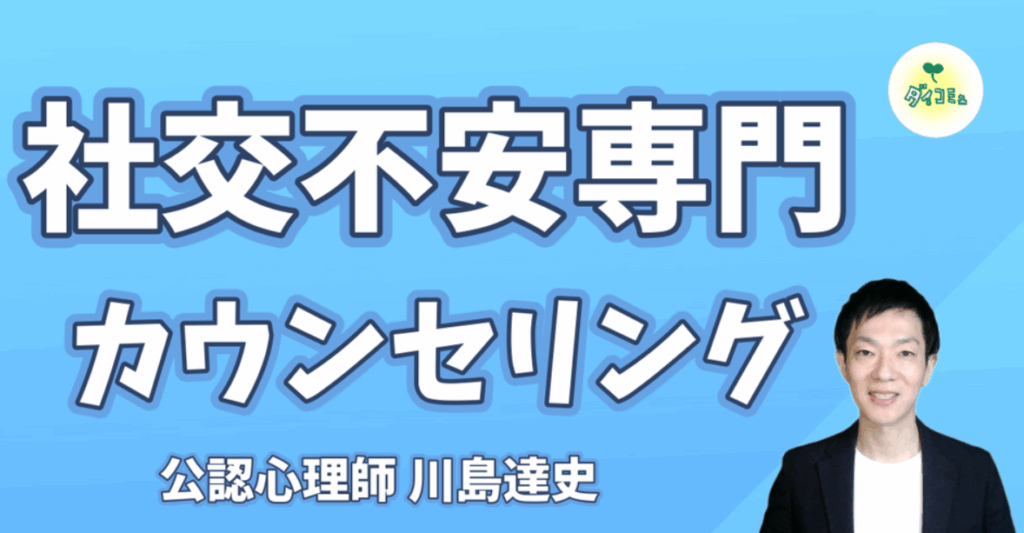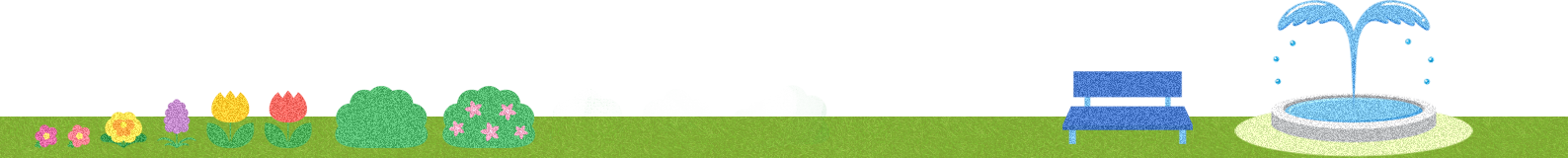こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。この記事では、社交不安症について基礎から解説します。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。
今回のテーマは①基礎編の「社交不安症の発症原因」です。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。
社交不安症の原因
社交不安症が発症する原因についてみていきます。
複合的な理由で発症
社交不安症は、ただ一つの原因で発症するものではありません。多くの原因が複雑に絡まりあって心に影響を与えています。それゆえ、社交不安症を理解し、改善するためには、原因を多面的に探っていく視点が必要です。
3つの視点
原因を探るうえで大切になるのが、「生理・心理・環境」3つの視点です。これは1977年にジョージ・エンゲルが提唱した「生理・心理・社会的モデル(Biopsychosocial model)」に基づいています。社交不安症を理解するには「生理・心理・環境」の3つの視点を総合的に見つめながら、どの点が自分に当てはまりやすいかを見つめ直すことが、原因を探るうえで大切です。
生理的な要因
社交不安症の生理的な要因には、脳の働きが関係しています。特に「扁桃体」と呼ばれる脳の部位が、恐怖や不安を感じる際に強く関与しています。社交不安症の方は、この扁桃体が過剰に反応しやすいとされており、ちょっとした対人場面でも強い恐怖心が生まれやすいのです。このように、身体の仕組みそのものが不安や恐怖を引き起こす土台になっていることがあります。
心理的要因
心のあり方や考え方のクセも、社交不安症の大きな原因のひとつです。たとえば、人と目が合っただけで「馬鹿にされているのでは」と感じるような、極端な自己否定的解釈をしてしまうことがあります。このような歪んだ認知は、コミュニケーションそのものを楽しむ余裕を奪い、不安や恐怖をさらに強めてしまいます。心理的な要因は、考え方の傾向や自己評価の低さと深く結びついています。
社会的要因
育ってきた生活環境や人間関係も、社交不安症の発症に大きな影響を与えます。たとえば家庭環境が悪く、安心して心を休める場所がなかった場合、自己肯定感や他者への信頼感が育ちにくくなります。本来、家庭はリラックスや愛情、信頼を育む場ですが、それを失うことで、人と関わること自体が怖くなってしまう人もいます。
生理的な要因
まずは身体の仕組みによる原因は、主に3つが関係していると考えられています。
①先天的な性格
社交不安症の原因のひとつに「先天的な性格」があります。これは単なる性格の問題ではなく、遺伝的な傾向として研究でも明らかにされつつあります。
たとえば、スウェーデンで1997年から2009年にかけて社交不安症や回避性パーソナリティ障害の方、約2万人を対象に行われた大規模な研究では、社交不安症の遺伝率が約56%にのぼることが示されました。
また、「行動遺伝学」と呼ばれる分野では、内向的でシャイな性格はおおよそ50%が遺伝によるものであるという知見もあります。つまり、「社交の場が苦手」「人前で緊張しやすい」といった傾向は、生まれ持った気質に由来することがあるということです。
②神経伝達物質の乱れ
社交不安症の背後には、脳内の「神経伝達物質」のバランスが深く関係していることが分かってきています。神経伝達物質とは、脳の中で情報をやりとりするための化学物質で、感情や行動、思考に大きな影響を及ぼします。なかでも重要なのが、セロトニンとドーパミンです。
たとえば、セロトニンは「安心感」や「安定感」をもたらす神経伝達物質で、これが不足すると、ほんの些細な刺激にも過敏に反応し、不安を感じやすくなります。また、ドーパミンは「やる気」や「快楽」に関わる物質で、分泌が少ない状態では、人と接していても「なんだか楽しくない」「意味がない」と感じてします。
神経伝達物質のバランスが崩れていると、社交場面において不安が高まりやすくなり、「会いたくない」「話したくない」という気持ちが強まってしまうのです。
③交感神経の過活動
社交不安症の身体的な要因のひとつに、交感神経の過活動があります。交感神経とは、自律神経の一種で、私たちの身体を活動的にする役割を担っており、緊張や不安を感じたときに心拍数を上げたり、発汗を促したりすることで、外的な刺激に対して迅速に反応できるよう身体を準備させる重要な仕組みです。
社交不安症の方の場合、この交感神経が過剰に働きすぎてしまうことがあります。たとえば、人前に立つだけで動悸が激しくなったり、手のひらや額に大量の汗をかいてしまいます。
さらに、身体の変化に強く意識が向き、それをなんとか抑えようとすればするほど、「もっと落ち着かなくては」「このままではおかしいと思われる」と不安が増幅されてしまいます。その結果、さらに交感神経が活性化し、身体症状が悪化するという悪循環に陥るのです。
心理的な原因
次に心のあり方による原因を5つの視点で見ていきます。
①公的自己意識が強すぎる
社交不安症の大きな心理的特徴のひとつに、「公的自己意識の強さ」が挙げられます。これは、他者からどう見られているか、どのように評価されているかに強い関心を持ちすぎてしまう傾向のことです。
たとえば、「周りにバカにされているのではないか」といった不安が常につきまとい、自分がどうしたいのかよりも、「他人にどう見られているか」が最優先されてしまいます。このような価値観や思考パターンが、日常的な人間関係を過剰に緊張させる原因となるのです。
この公的自己意識は、思春期のタイミング(小学6年生から中学3年生頃)にかけて、急速に高まるとされており、社交不安症の初期症状が現れやすい時期とも一致しています。この時期に過剰な評価への不安が形成され、それが長年にわたり根強く残ることで、大人になってからも社交場面に強い苦手意識を抱えるようになるケースが少なくありません。
②失敗過敏
社交不安症の人が抱えやすい心理のひとつに、「失敗してはならない」という強い思い込みがあります。これは「失敗過敏(しっぱいかびん)」とも呼ばれ、対人場面でのあらゆるやり取りにおいて、ミスや失敗を極端に恐れる傾向です。
たとえば、会話をしているときに「言葉に詰まってはいけない」「沈黙が生まれてはいけない」といった不安に支配され、自然なコミュニケーションが困難になります。本来であれば多少の失敗や沈黙は誰にでもあるものですが、社交不安症の人はそれらを過度に重大なものと捉え、「失敗=否定されること」と直結させてしまいます。
このような「失敗してはならない」というプレッシャーは、実際の会話を不自然でぎこちないものにし、結果的に「うまく話せなかった」という自己評価を生み、不安や恐怖をさらに強めてしまう悪循環につながります。
③安全行動をとるクセ
社交不安症の人がよく取ってしまう行動のひとつに、「安全行動」と呼ばれるものがあります。これは、不安を感じる状況を避けることで、一時的な安心感を得ようとする心の癖のようなものです。
たとえば、人と会話をすることに強い不安を感じている人が、会社の昼休みに同僚と食事をするのが怖くて、毎日外食を選ぶようになるといった行動です。このような選択は、当面の不安を和らげるには効果がありますが、長い目で見ると問題の根本的な解決にはつながりません。
安全行動を続けていると、少しずつ「人と食事をすること」「会話をすること」といった日常的な社会活動の経験を積む機会を失い、「自分にはできない」という思い込みが強化され、不安感や恐怖心がさらに大きくなってしまうのです。
④見捨てられ不安
社交不安症の方の中には、「見捨てられ不安」を抱えている方が少なくありません。「人前で失敗したら、きっとみんなに嫌われるに違いない」といったように、極端な推測や思い込みが不安をさらに強めてしまうのです。
まず、見捨てられ不安とは、「この人はいつか自分の元からいなくなってしまうのではないか」といった恐れの感情で、幼少期に愛情を十分に受けられなかった経験がある人に見られやすいとされています。
見捨てられ不安が強いと、他者との関係の中で常に「自分は見捨てられるかもしれない」という警戒心を抱いてしまい、人との関係を築くこと自体が怖くなったり、逆に必死に相手に合わせすぎて自分を見失ってしまうこともあります。こうした状態が続くと、自己肯定感が低下し、ますます人間関係に対して消極的になってしまう悪循環に陥ります。
⑤否定的な妄想と思い込み
社交不安症の方にしばしば見られる特徴のひとつに、「非現実的な妄想」があります。これは、実際の出来事や相手の言動に対して、極端に否定的で、かつ現実離れした解釈をしてしまう思考のクセです。
たとえば、
-
「みんなが自分のことをバカにしているに違いない」
-
「もしスピーチで失敗したら、人生は終わりだ」
-
「あの人が笑ったのは、自分を馬鹿にしているからだ」
-
「誰かが優しくしてくれるのは、裏があるに違いない」
こうした考え方は、根拠がないにもかかわらず本人にとっては強い現実感を伴っており、そのため頭の中で何度も繰り返され、不安や恐怖をどんどん増幅させてしまいます。
生活環境に由来する原因
最後に生活環境について4つのポイントから見ていきます。
①会話のない生活
まず挙げられるのが「会話のない生活」です。会話が少ない生活を続けていると、人の話をどのように聞けばよいのか、自分の話をどう展開していけばよいのかといった、コミュニケーションに必要な技術的な経験値が十分に積み重ならないままになってしまいます。その結果、人間関係を築くための力が徐々に衰えていくことになります。
このような状況になると、いざ友達を作ったり恋愛を始めたりしようとしても、心を開いて相手とどう関わればよいのか、具体的な手がかりが全くなく、不安や戸惑いが大きくなってしまいます。そのため、「自分には人と関わる力がない」と感じやすくなり、不安がどんどん増していくのです。
②家庭環境が悪い
家庭環境が悪いことも、社交不安症を悪化させる要因のひとつとして挙げられます。家庭は心が最も落ち着き、リラックスできる場所であり、愛情をお互いに交換し合いながら、傷ついた心を癒す空間でもあります。しかし、そのような心を癒し回復させるべき場所が、逆に心を傷つけたり悪化させたりする環境である場合、一体どこで自分の心を取り戻せばよいのか分からない、という状況に陥ってしまいます。
その結果、家庭でさえ安心できない状態では、外の人間関係に挑戦することがより困難となり、不安や恐怖が一層強まってしまうのです。社交不安症の方の中には、このような悪い家庭環境で育った方が多いことも特徴の一つとなっています。
③いじめ、パワハラ
たとえ家庭環境が良好であっても、外部でのストレスが強い場合には社交不安症が悪化しやすくなります。具体的には、学校や職場でのいじめやパワハラが挙げられます。
いじめやパワハラは、人の人格や存在そのものを否定するような行為であり、これを長期間受け続けると、心は大きく傷つき、自己肯定感は著しく低下します。心のダメージは、外の世界に対して恐怖心を抱かせ、「人と関わることが怖い」「自分には価値がない」という感覚が強まります。こうした環境で過ごすことは、社交不安症の悪化を招く大きな要因となります。
④日本特有の教育
日本の教育もまた、社交不安症の発症や悪化に影響を与える重要な要素です。日本では「迷惑をかけてはいけない」という価値観が非常に強く、小さい頃から公共の場でのマナーや集団行動が厳しく指導されます。たとえば、電車では静かにすること、ゴミは持ち帰ること、列にきちんと並ぶことなど、集団生活のルールや規律が厳格に守られています。
このような文化は秩序を保ち、暮らしやすい社会を作る上で非常に大切ですが、行き過ぎると自己犠牲的な態度が強くなり、「他人に迷惑をかけてはいけない」という思いが過剰に働いてしまいます。その結果、人と接する際に「自分が迷惑をかけるのではないか」と過度に心配し、恐怖心や不安が増幅してしまうケースがあります。精神医学の診断基準には、「文化依存症候群」という項目があり、日本人に特有の対人恐怖症として分析されていることもあります。
ゆっくり改善を目指そう
社交不安症の方の心の中は、多くの原因が絡み合った糸の塊のように複雑に絡まっています。この複雑に絡み合った糸を一気にほぐそうとしても、うまくいかないことが多いのです。一つ一つの糸を丁寧にほぐしながら、「この糸はここを通すと上手くいくのではないか」と慎重に進めていくことが必要となります。
一度にすべてを解決しようとせず、一つ一つ丁寧に問題を解消していく心構えを持ち、ゆっくりと改善していくことを大切です。
次回のコラムに進む
今回は社交不安症の基礎編④を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。
カウンセリングのご案内
筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。